人々は今年の七夕のことなんてとっくに忘れているだろう。しかし、七夕(たなばた、しちせき)は五節句の一つであり、旧暦(太陰太陽暦)で祝うべき日である。その旧暦七月七日が今年は8/29なのだ。
「ええっ、なんで今頃?」と驚かれるかもしれないが、今年は旧暦六月のあとに【閏(うるう)六月の29日間】が挿入されたので、ようやく8/23 「処暑」の日(黄経150° 旧暦七月の中気)が旧暦七月朔日(ついたち)だったのだ。そこから数えて七日目が昨夜の七夕だった。
閏月の無い普通の年でも新暦の7/7からひと月ほど遅れて旧暦七月七日はやってくる。新暦7/7は未だ梅雨の明けやらぬ時期で、大概は大雨である。明治政府が暦法を太陽暦に変えたときに旧暦も残して併用すればよかったのだが、維新政府は ―廃仏毀釈でも知られるように― 旧暦に根差す伝統文化を破壊しまくった。
太陰太陽暦は、月の満ち欠けという、目で見て毎日の変化が分かり易いばかりでなく、太陽暦とのズレを補正するべく二十四節季を固定し、3年に一度の閏月挿入という方法を編み出していた。ちゃあんと農事に整合した暦だったのである。江戸時代のものは何でもかんでも旧弊として貶めるように、意図的に維新政府は画策したように思える。因みに、当地近辺に多い「天保義民の碑」が立派なのも、維新政府が徳川幕政を貶めるべく明治期にプロパガンダとして建立したものと考えている。
そんな政府のゴリ押しに従う必要はないのだが、神社や寺で新暦にて催事を執り行うというのは不見識だと私は思う。例えば、旧表記・大阪府北河内郡交野(かたの)町大字倉治(おおあざ くらじ)にある我が生家の真前は「機物(はたもの)神社」である。名前からして機織りの神様を祭っているかと連想されよう。事実、タクハタチヂヒメという女神が主祭神とされる。 この神社が新暦7/7に七夕祭を催行する。私がガキのころは華やかな祭りは何もない地味な神社だった。しかし、いつの頃からか、若者受けのする七夕祭を派手派手しくやり始めた。つまりはオリンピックなどと同じ商業主義なのだ。商売としてやるのなら、伝統に立ち返って、好天の多い旧暦でやればよいものを、大雨の多い梅雨時にやっている。
出雲大社は今日(こんにち)でも旧暦で神事を執り行っている。見識であると思う。旧暦十月十日の夜8時頃に稲佐の浜で神迎え神事が催行される。全国津々浦々から八百万(やおよろづ)の神々が浜に上がって来られる。この時期、出雲の海は「お忌み荒れ」という強烈な季節風が吹き始めるのだが、神迎え神事の間は風も和らぎ、南東の空の雲間に十日月が暖か味のある光を投げかけ波々を照らす。陰暦だからこそ、毎年決まって十日月のもとで神事が行われるのである。
さて、昨夜(8/29)夜8時に三雲クリニックの前に出て空を眺めると、天頂にベガ(織女星)、そこから東方にデネブ、天頂から真南に少し下がってアルタイル(彦星)がハッキリ見えた、快晴であった。周りの空が明るいので、天の川は我が老眼ではボンヤリしか見えない。しかし、七日月は南西の空に既に低く(高度10°くらい)、天頂近くの星々や天の川を邪魔しない。七という月齢ならではの好配置なのだ。新暦ではこうはならない。 上記の3星は「夏の大三角」を為すことを復習もした。風も若干涼しく、虫の音も秋を感じさせる。
国立天文台(NAOJ)も旧暦七夕を尊重して「伝統的七夕」を鑑賞することを奨めている。同サイトには2025/8/29 20時頃の東京の星空を美しく掲げてある。是非ともご覧あれ。https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/08-topics06.html

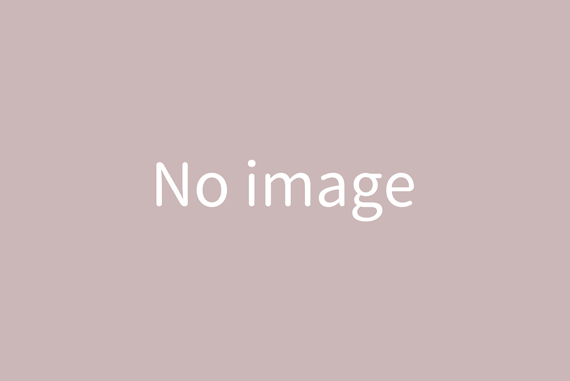
三雲クリニック
R7/11/29 旧暦十/十 今夜は出雲・稲佐ノ浜に神々が上陸される神迎祭。十日月を背景に、かがり火を焚いて